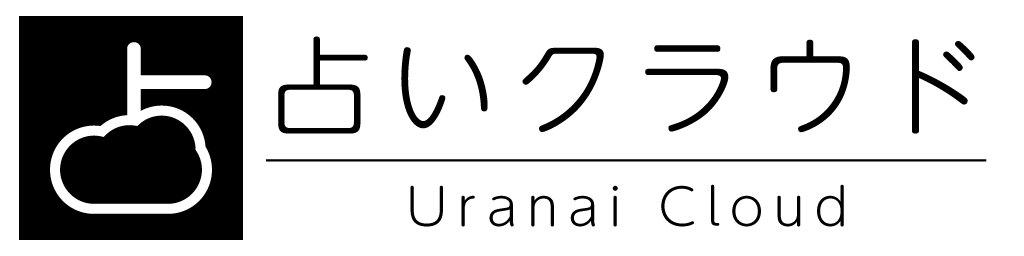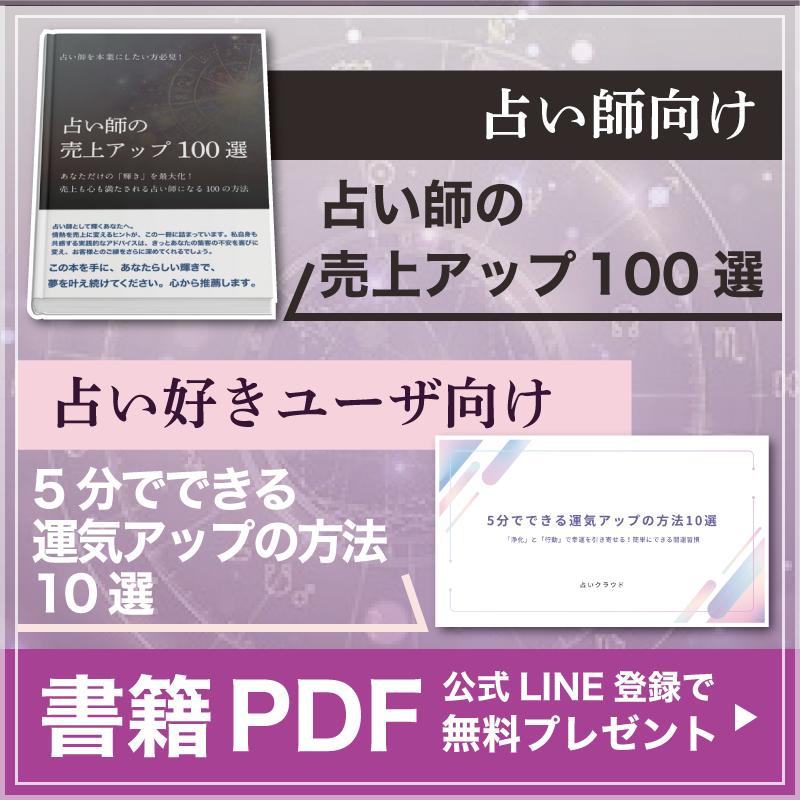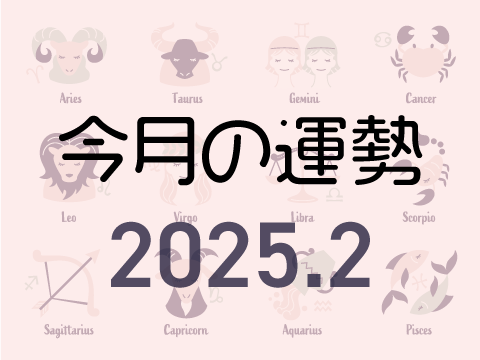年末に飾ったしめ飾り、ふと「これって、いつまで飾っていいんだろう?」と迷いますよね。結論から言うと、目安は「松の内」が終わるまで。ただし松の内は地域差があり、さらにどんど焼き(お焚き上げ)の予定によってもベストな外し方が変わります。この記事では、しめ飾りを外す時期、処分方法、飾り始めのタイミングまで、迷わない形でまとめます。
目次
しめ飾りはいつまで?
しめ飾りを外す基本のタイミング
しめ飾りを外す基本のタイミングは「松の内が終わったら」です。松の内は、年神様をお迎えしている期間とされ、しめ飾りはその目印のような役割を持ちます。だから、松の内が終わったら外して区切りをつける、という流れが自然です。迷ったら、松の内の最終日の夜ではなく、翌日の朝に外すと落ち着いて動けます。急いで正解を探すより、丁寧に区切りをつける意識が大切です。
松の内が地域で違う
松の内は全国で同じではなく、地域によって期間が違います。そのため「いつまで?」の答えが一つに決まりません。よく言われる目安は、関東は1月7日まで、関西は1月15日まで。ただし、この区分もあくまで代表例で、地域の慣習や神社の案内に沿うのが一番安心です。家族や近所で昔からの流れがあるなら、それに合わせる方が気持ちよく区切れます。
迷ったら「地元ルール優先」にする
どうしても迷ったら、「地元のルールを優先する」で大丈夫です。しめ飾りは生活文化なので、カレンダーの正解より“その土地の流れ”に馴染ませる方が自然です。近所の神社が「松の内はいつまで」と掲示していたり、どんど焼きの日程を案内していることもあります。自分の家だけで判断が難しいときは、地域の案内に合わせるのが最もスムーズです。
松の内はいつまで?
関東はいつまでが多い?(1月7日目安)
関東では、松の内を1月7日までとする地域が多いと言われます。その場合、しめ飾りは7日まで飾り、8日の朝に外す流れが分かりやすいです。年明けの慌ただしさが落ち着いたころに区切りが来るので、片付けも進めやすいのが特徴です。もし7日が忙しいなら、前日の夜に外すより、翌朝に落ち着いて外す方が丁寧で気持ちよく終われます。
関西はいつまでが多い?(1月15日目安)
関西では、松の内を1月15日までとする地域が多いと言われます。この場合、しめ飾りは小正月まで飾る感覚に近く、ゆっくり正月の空気を味わうイメージです。15日まで飾るなら、16日の朝に外すのが区切りとして分かりやすいでしょう。地域によっては、どんど焼きの日程もこのあたりに集中することが多いので、処分まで一気に流れを作りやすいのもメリットです。
例外(1月20日まで等)がある地域の扱い
中には、松の内を1月20日頃までとするなど、例外的な地域もあります。また、同じ県内でも地域差が出ることも珍しくありません。この場合は「周囲の家がいつ外しているか」「地元の神社がいつまでとしているか」を参考にすると判断しやすいです。しめ飾りは“飾ってはいけない日”が厳密に決まっているというより、迎えて見送る流れが大事なもの。土地の慣習に合わせて自然に区切りましょう。
しめ飾りはいつ外す?状況別のベストタイミング

松の内が明けたら外す
いちばんシンプルなのは、松の内が明けたタイミングで外す方法です。松の内の最終日まで飾り、翌朝に外して片付ける。これなら迷いがなく、家族に説明もしやすいです。
外すときは、ただ撤去するより「ありがとうございました」と心の中でひとこと添えると気持ちが整います。急いで処分まで進めなくても、まずは外して清潔にまとめておくだけで十分です。
小正月の行事に合わせて外す
地域によっては、小正月(1月15日頃)の行事に合わせて外す家庭もあります。正月飾りを片付けることで、年始のモードから通常の生活へ切り替える意味合いが強くなります。
小正月まで飾る場合は、しめ飾りが傷んでいないか、汚れが目立っていないかだけ確認すると安心です。もし途中で破れたり落ちたりしていたら、無理に引き延ばさず、状態に合わせて外して構いません。
どんど焼きの日程に合わせて外す
どんど焼き(左義長)に持っていく予定があるなら、その日程に合わせて外すのも合理的です。外してから長く家に置くより、直前に外してそのまま持参できるとスムーズ。
ただし、玄関に何もない期間が気になる場合は、松の内明けに外して保管し、当日に持っていく形でもOKです。大切なのは、外した後に乱雑に置かず、袋にまとめて清潔に保管することです。
外したしめ飾りの処分方法
どんど焼き(左義長)で納める
最も一般的で気持ちよく手放せるのが、どんど焼きで納める方法です。地域の神社や広場で行われる行事で、正月飾りをお焚き上げして一年の無病息災を願う流れがあります。持参するときは、ビニール袋に入れて運び、現地のルールに従って分別するのが安心です。時間帯が決まっていることも多いので、事前に案内を確認しておくと当日バタつきません。
神社のお焚き上げ・古札納所に納める
どんど焼きの日に行けない場合は、神社の古札納所(古いお札やお守りを納める場所)に納める方法があります。お焚き上げを受け付けている神社もあり、正月飾りも一緒に納められるケースがあります。ただし神社によって受付の可否や期間が違うので、掲示や公式案内を確認すると安心です。納めるときは、感謝の気持ちを添えて静かに置く。それだけで十分丁寧です。
行けない時の自宅処分
塩で清めて自治体ルール
どうしても持っていけない場合は、自宅で処分しても問題ありません。まず感謝の気持ちを込めて外し、白い紙などの上に置いて塩をひとつまみ振り、気持ちとして清めます。その後は、自治体の分別ルールに従って処分します。しめ飾りは素材が混在していることが多いので、可能なら分けて捨てると安心です。大事なのは、雑に捨てるのではなく“区切りをつけて手放す”意識です。
しめ飾りはいつから飾る?
飾り始めの目安(正月事始め以降)
しめ飾りを飾り始める目安は、年末の準備が整ってきた頃です。一般的には正月事始め(12月13日)以降なら準備期間として自然で、そこから年末にかけて飾る家庭が多いです。とはいえ、早すぎると気持ちが追いつかないこともあるので、「大掃除が一段落した」「玄関周りが整った」タイミングで飾ると、見た目も気分もきれいにまとまります。
飾ると縁起がいい日(12/28など)
飾る日としてよく選ばれるのが12月28日です。末広がりの「八」に通じるとして、縁起が良いと感じる人が多い日です。もちろん他の日でも問題はありませんが、迷うなら28日にするとスムーズです。年末は予定が詰まりがちなので、余裕のある日に飾るのがいちばん。飾る日は、玄関を軽く拭いてから取り付けると、しめ飾りの意味である“清め”と行動が揃って気持ちが整います。
避けたい日(12/29・12/31など)
避けた方がいい日としてよく挙がるのが12月29日と12月31日です。29日は「二重苦」を連想すると言われ、31日は“一夜飾り”になり慌ただしい印象になりがち。とはいえ、絶対にダメというより「できれば避けたい」程度に捉えると現実的です。もし31日しか時間がないなら、雑に飾るより、玄関を整えて丁寧に取り付ける方が大事。日にちより所作の丁寧さが整えになります。
しめ飾りの飾り方と注意点
玄関に飾るときの基本
しめ飾りは基本的に玄関の外側、目線より少し高い位置に飾ることが多いです。場所が難しい場合は、内側でも構いませんが、清潔な位置を選ぶと気持ちが整います。取り付ける前に玄関周りの埃をさっと払うだけでも、しめ飾りの意味と行動が一致してきれいです。飾りが傾いていると見た目が乱れるので、正面から見てまっすぐになるように整えるのがポイントです。
マンションで飾るときの注意
マンションでは、玄関扉の外側が共有部扱いになる場合があります。ルールによっては装飾がNGのケースもあるので、気になるなら管理規約や掲示を確認すると安心です。外側が難しい場合は、玄関内側に飾っても問題ありません。固定方法は、強い粘着テープで扉を傷つけないよう注意し、マスキングテープ+フックなどで負担を減らすと安全です。落下しないことが最優先です。
しめ飾りが古くなった
壊れた時の判断
飾っている途中でしめ飾りが破れたり、雨で傷んだりした場合は、無理に期限まで飾り続けなくて大丈夫です。しめ飾りは“清めと区切り”の象徴なので、ボロボロの状態で放置すると逆に気持ちが乱れやすい。壊れたら早めに外し、丁寧にまとめて処分のルートへ回しましょう。代わりを用意できるなら付け替えもOKですが、できなくても「外して整えた」時点で役割は果たしています。
しめ飾り に関するスピリチュアル的な捉え方

しめ飾りは何のため?(結界・歳神様を迎える目印)
しめ飾りは、外からの穢れを防ぎ、家の内側を清める“境界”の象徴とされます。スピリチュアル的に言えば、玄関にしめ飾りがあるだけで「今年はこう生きる」という宣言を外に出しているようなもの。歳神様を迎える目印とも言われ、年のはじまりに意識を切り替える装置として機能します。だからこそ、飾る前に玄関を整え、飾った後は丁寧に扱うほど、気持ちの切り替えが強くなります。
外す日は「見送る儀式」として整える
外す日は、ただ片付ける日ではなく“見送る日”と捉えると気持ちが整います。松の内が明けたら、玄関で一呼吸して、感謝の気持ちを添えて外す。それだけで、正月モードが落ち着き、日常のリズムに戻りやすくなります。スピリチュアルは形より意識が大事なので、豪華なしめ飾りかどうかは関係ありません。丁寧に区切りをつけるほど、年の流れを自分のペースに戻せます。
外した後に運気を落とさないコツ
外した後に運気を落とさないコツは、玄関を少しだけ整えることです。しめ飾りを外して終わりにするより、扉やドアノブを拭き、靴を揃えて、明るい空気を作る。これだけで“結界を外した後の整え”が完了します。スピリチュアル的には、運は清潔さと習慣に宿りやすいので、玄関が整うほど流れがよくなる感覚が生まれます。大掃除ほど頑張らなくていいので、1分だけ整えるのが効きます。
具体的な行動
今日やるなら:地域の松の内を確認する
まずは、あなたの地域の松の内がいつまでかを確認します。関東・関西の目安はありますが、地域差があるため、近所の神社の掲示や自治体の案内、家族の慣習がいちばん確実です。さらに、どんど焼きがあるなら日程もセットで確認すると、外す日と処分の日を一気に決められます。「いつまで?」で迷う時間を減らすほど、片付けも気持ちもスッと進みます。
外す日:朝に外して、袋にまとめて保管する
外す日は、できれば朝に行うと落ち着いて進められます。外したら、そのまま床に置かず、紙や袋にまとめて清潔に保管しましょう。特にどんど焼きまで日が空く場合、玄関に置きっぱなしにすると散らかって見えるので、目に入らない場所に一時保管するのがおすすめです。外すときは「ありがとうございました」と心の中で添えるだけで区切りがつき、年始の空気から日常へスムーズに戻れます。
処分:どんど焼き/神社/自宅処分のルートを決める
処分方法は、どんど焼きに持っていくのが一番スムーズですが、難しければ神社の古札納所やお焚き上げ受付を利用します。それも難しい場合は、塩で清めて自治体ルールに従って処分してOKです。大切なのは、ルートを決めておくこと。いつまでも置きっぱなしだと気持ちが引っかかるので、「この日に持っていく」「この日に処分する」と決めるだけでスッキリします。
よくある質問(FAQ)
Q: いつまで飾る?
A: 基本の目安は「松の内が終わるまで」です。関東は1月7日まで、関西は1月15日までとされることが多いですが、地域差があります。迷ったら、近所の神社の案内や家族・地域の慣習に合わせるのが安心です。外すのは最終日の夜より、翌朝に落ち着いて外す方が丁寧。感謝の気持ちを添えて外すと、正月の区切りがきれいに付きます。
Q: どんど焼きはいつ?
A: どんど焼き(左義長)は小正月の1月15日前後に行われることが多いですが、地域によって日程がずれます。神社や自治体の案内で「受付日」「持ち込み時間」が決まっているケースもあるので、事前確認が安心です。どんど焼きに合わせるなら、当日か前日に外して袋にまとめるとスムーズ。行けない場合の代替ルートも決めておくと、正月飾りを気持ちよく手放せます。
Q: 捨てても大丈夫?
A: 大丈夫です。どんど焼きや神社への返納が難しい場合、自宅で処分しても問題ありません。外したら白い紙などの上に置き、塩をひとつまみ振って気持ちとして清め、あとは自治体の分別ルールに従って捨てます。しめ飾りは素材が混在しがちなので、可能なら分別すると安心です。大切なのは雑に捨てることではなく、感謝して区切りをつけて手放す意識です。
まとめ
しめ飾りは「松の内が終わるまで」が基本の目安ですが、地域差があります。関東は1月7日、関西は1月15日がよく挙げられますが、迷ったら地元の慣習や神社の案内に合わせるのが安心です。
外したしめ飾りは、どんど焼きや神社へ納めるのがスムーズで、難しければ塩で清めて自治体ルールで処分してOK。外す日は“見送る日”として丁寧に区切りをつけ、玄関を少し整えると気持ちも運の流れもスッと整います。