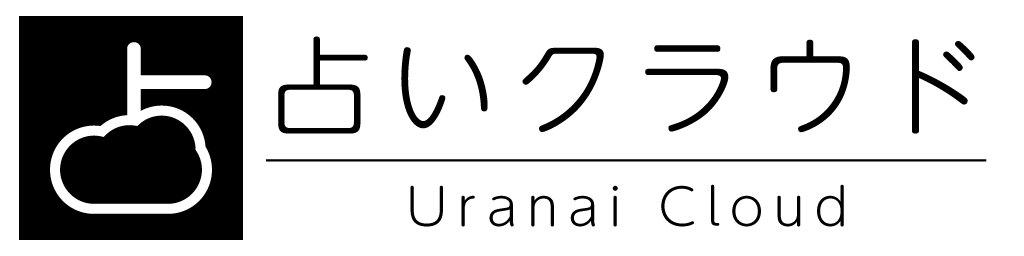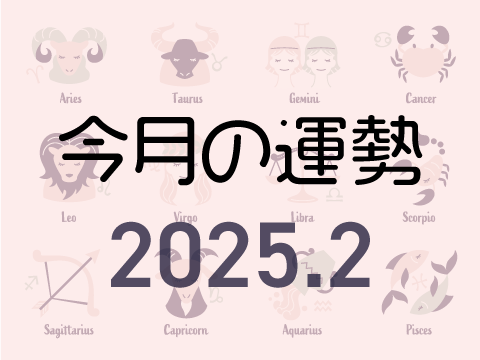数え年(かぞえどし)は、生まれた瞬間を1歳とし、元日(1月1日)を迎えるたびに1歳ずつ加算する日本の伝統的な年齢の数え方。現在の日本では多くの場面で満年齢(誕生日ごとに年齢が増える)が使われるが、七五三や厄年などの伝統行事では数え年が用いられることがある。
目次
数え年の数え方
数え年早見表
※数え年の簡易計算方法:新暦1月1日基準なら、対象年の数え年=「対象年 − 出生年 + 1」
満年齢との違い
- 数え年:出生「1歳」開始。新年(1月1日)ごとに加算。
- 満年齢:出生「0歳」開始。誕生日ごとに加算。
数え年が使われる主な場面
現在の使われ方
日常生活や公的手続きは満年齢が基本。数え年は一部の神事・伝統行事・地域習慣で継承されている。
よくある質問
数え年の計算はどうする?
対象年 − 出生年 + 1。
例:2000年生まれの2025年は 2025−2000+1=26。
どんな場面で使う?
厄年、七五三、賀寿(喜寿・米寿・白寿など)、神社の祈祷で用いられる。一方、法律・学校・保険・公的手続きは満年齢が基本。
早生まれや2月29日生まれの扱いは?
誕生日は関係なく、全員が元日(1/1)に一斉に1歳加算。うるう年の有無も影響しない。
厄年は数え年で数えるの?
多くの神社は数え年基準。男性は本厄25・42・61歳、女性は本厄19・33・37歳(前厄・後厄は各1年)。地域や神社で基準が異なるため案内を確認。
元日の基準は新暦?旧暦?
現在は新暦の1月1日が主流。伝統を重んじる地域・寺社では旧正月基準の場合もあるため、参加先の案内を確認すると確実。